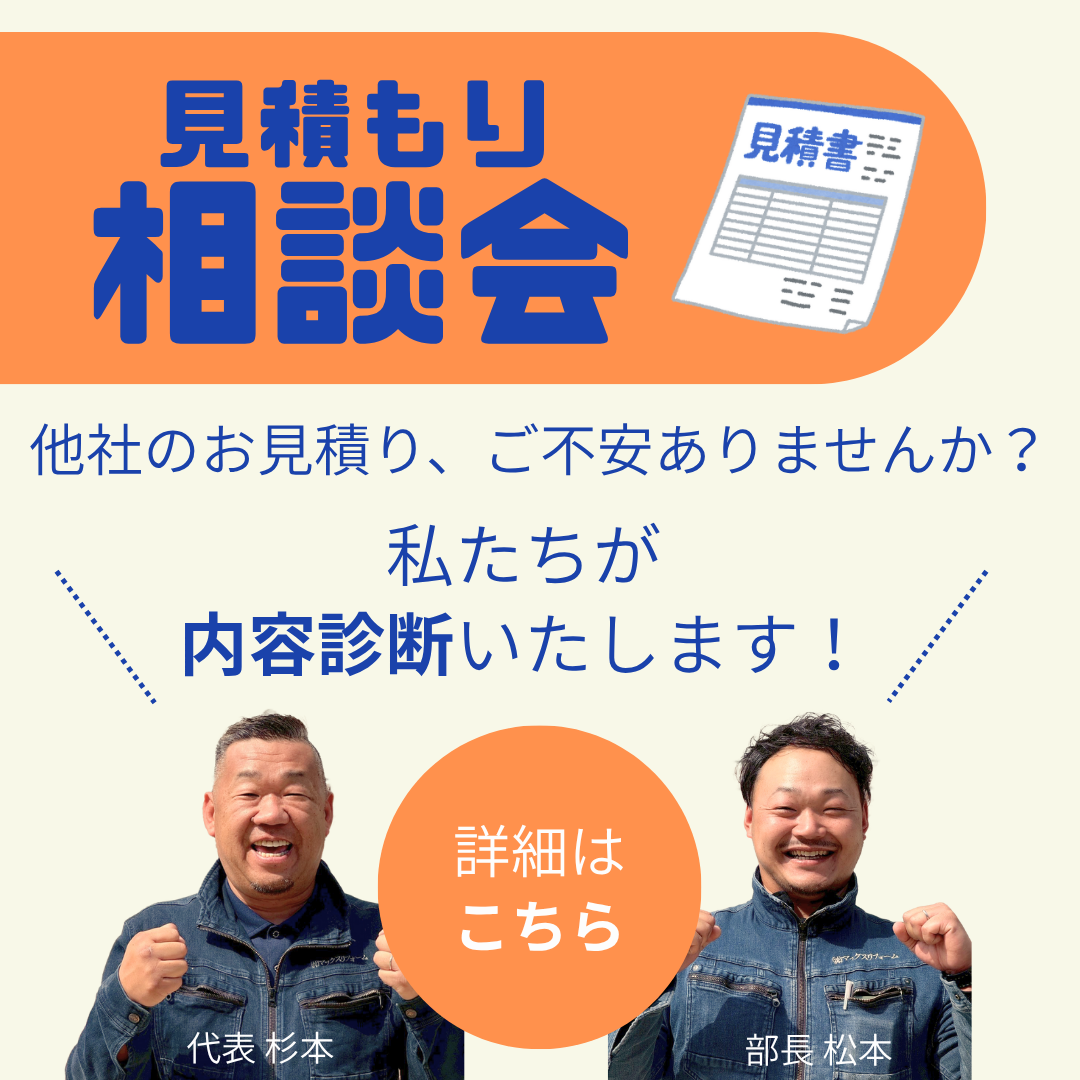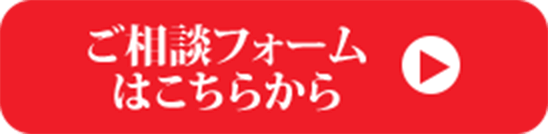屋根の垂木(たるき)サイズはどう決まる?住宅タイプ別の基準を解説

屋根の構造において「垂木(たるき)」は非常に重要な部材です。
屋根材の下にあり、屋根の勾配を形づくる骨組みの一部として、屋根全体の強度や耐久性に大きく関わっています。
この記事では、「垂木サイズはどう決まるのか?」という疑問に対し、住宅の種類や屋根形状による基準の違い、
そして安全性・耐震性に配慮した垂木サイズの考え方について、建築実務の視点から詳しく解説します!
垂木(たるき)とは何か?屋根構造における役割を確認しよう
垂木とは、屋根の勾配に沿って配置される木材(または金属)のことで、屋根材や野地板を支える役目を果たします。
垂木は母屋や棟木から軒先に向かって取り付けられ、屋根全体の荷重を分散しながら、雨や雪、風などの外的要因に耐える構造を作り上げます。
主な役割
- 屋根材・野地板を支える
- 屋根の荷重を構造体に伝える
- 屋根勾配を形成する
- 通気・断熱の確保に関与する
垂木は屋根の構造的安定性を担う重要な部材。サイズ選定は極めて重要!
垂木サイズの基本|厚みと幅の目安
垂木のサイズは、主に「厚み(断面の高さ)」と「幅(横幅)」で表されます。
一般的な垂木サイズの例
- 45mm × 60mm(小規模木造住宅)
- 45mm × 90mm(一般的な在来工法住宅)
- 60mm × 105mm(スパンが長めの屋根や積雪地域)
これらのサイズは、屋根のスパン(垂木の長さ)、屋根勾配、屋根材の重量、地域の気候条件(積雪量・風圧)などによって変わってきます。
垂木サイズを決める要素とは?
垂木サイズは、次のような複数の要素を総合的に考慮して決定されます。
スパン(垂木の長さ)
長いほど荷重がかかりやすく、太い垂木が必要。
屋根の勾配
急勾配の屋根は荷重のかかり方が分散されるため、細めでも対応可。
屋根材の重量
瓦やガルバリウム鋼板、スレートなど、素材ごとに必要な垂木の強度が異なる。
積雪・風圧などの外的荷重
雪の多い地域や台風常襲地域では、垂木のサイズを大きくする必要あり。
垂木の間隔(ピッチ)
ピッチが広いと一つひとつの垂木にかかる負担が増す。
住宅タイプ別|垂木サイズの目安
在来工法(木造軸組工法)
- 一般的な屋根スパン:約910〜1,200mm
- 推奨垂木サイズ:45×90mm〜60×105mm
木造住宅で最も多く見られる工法。柱と梁によって支えられる構造のため、垂木のサイズはやや大きめに設定されます。
2×4工法(ツーバイフォー)
- 壁構造が主体となるため、屋根荷重が分散されやすい
- 推奨垂木サイズ:38×89mm(2×4材)や38×140mm(2×6材)
構造自体が耐力壁を主体とするため、垂木への荷重が少なめですが、スパンが長い場合は太めの垂木が必要です。
RC造(鉄筋コンクリート住宅)
- 木造に比べて屋根が軽量化されやすく、装飾的な屋根が多い
- 推奨垂木サイズ:設計条件によって大きく異なるが、一般的には60mm以上の木材を使用
鉄骨下地や屋根パネル工法が使われるケースも多く、垂木自体が設置されないこともあります。
垂木サイズと構造強度の関係

垂木は屋根の骨組みを構成する重要な部材であり、そのサイズ(断面寸法)は構造全体の強度を大きく左右します。
適切なサイズを選ぶことで、屋根のたわみ・変形・崩壊を防ぎ、安全かつ長寿命な建物を実現できます。
垂木サイズが強度に与える影響
垂木の「強度」とは、主に以下の2つの指標によって左右されます。
- 断面二次モーメント(曲げ強度):断面が大きいほど、たわみにくくなり、屋根全体の安定性が高まります。
- 断面係数(応力分布の中心):荷重がかかる部位での耐力が高くなるため、変形や破損リスクが減ります。
たとえば、同じ材質でも「45×90mm」と「45×60mm」の垂木では、曲げ強度が約2倍違うこともあります。
樹種や含水率による影響
同じ寸法でも、使用する木材の種類や含水率によって強度は変わります。
- ヒノキや米松は、スギよりも曲げ強度に優れ、スパンの大きな屋根にも対応しやすい。
- 乾燥材(KD材)を使うと、湿気による変形や収縮が抑えられ、長期的な安定性に寄与します。
スパン(垂木の支え間隔)とのバランス
垂木サイズを決定する際は、垂木の「スパン」=支点間距離が重要です。
- スパンが広いほど、垂木がたわみやすくなるため、断面を大きくして対応します。
- たとえば、スパン1.8mまでは45×60mm、スパン2.7mでは最低でも45×90mm以上が推奨されることが多いです。
雪・風・地震といった外力への備え
構造設計では、積雪荷重・風圧・地震時の揺れを考慮する必要があります。
- 積雪地帯では、積載される雪の重みに耐えられるよう、垂木のサイズアップが必須。
- 沿岸部や台風の多い地域では、風圧を受けにくいよう、垂木を太くし、金具補強も加えます。
強度確保だけでなく「ねじれ」や「割れ」も意識
垂木は単に荷重に耐えるだけでなく、ねじれや反りへの耐性も必要です。細くて長い垂木は、施工後の乾燥や熱収縮により、
- 曲がり
- 割れ
- 屋根材の浮き
などの不具合を引き起こす原因になるため、サイズ選定時は「剛性」だけでなく「寸法安定性」も意識しましょう。
建築基準法との関連
日本の建築基準法では、特定の建物用途や構造形式に応じて「構造耐力上主要な部分」に該当する垂木サイズの基準が定められています。
許容応力度計算を行う場合、木材の種別や使用条件によって「許容曲げ応力度」「せん断応力度」も確認が必要です。
垂木のピッチ(間隔)と強度のバランス

垂木のピッチとは、隣り合う垂木の中心から中心までの間隔を指します。このピッチは、屋根の強度や耐久性、施工コストに大きな影響を与える重要な設計要素です。
一般的なピッチの基準
- 455mm(1.5尺):日本の木造建築で最も多く採用されている寸法。垂木の本数は多くなりますが、屋根全体の剛性を高く保ちやすく、安定性にも優れます。
- 910mm(3尺):間隔を広くとることで材料の節約につながりますが、その分垂木1本にかかる荷重は大きくなるため、垂木のサイズアップが必要です。
ピッチと垂木サイズの相関
ピッチを広げると、垂木自体にかかる負担が増えるため、断面寸法(厚み・幅)を大きくして補う必要があります。たとえば、
- ピッチ455mm → 45×60mmの垂木でも対応可能なケースが多い
- ピッチ910mm → 45×90mm以上、場合によっては60×105mmのサイズが望ましい
ピッチを狭くするメリット・デメリット
メリット:
- 荷重が分散されるため、構造的に安定
- 屋根材のたわみや割れを防ぎやすい
デメリット:
- 垂木の本数が増えることで材料費・施工費が上がる
- 施工時間が長くなる
ピッチと屋根材の相性
屋根材ごとに、適した垂木ピッチが異なります。たとえば:
- 瓦屋根:重い屋根材のため、ピッチは455mm以下に設定するのが一般的
- スレート・金属屋根:軽量なため、ピッチを広めに取っても対応可能
耐風・耐雪設計との関係
地域によっては、風圧や積雪に対する設計基準が厳しくなるため、ピッチを狭めて剛性を高めることが必要です。
垂木サイズ選定の際の注意点

垂木サイズを決める際には、以下のような具体的な注意点があります。
建築基準法や地域の構造基準を確認する
建物の規模や構造によって、使用できる垂木のサイズには法的な基準があります。地域ごとの積雪荷重や風圧荷重の基準に応じた設計が必須です。
材質による強度の違いを理解する
同じ寸法でも、杉やヒノキ、集成材、輸入材(SPFなど)によって強度や耐久性が異なります。材質選びもサイズ設計と同等に重要です。
接合部の強度や金物の選定も併せて行う
垂木自体が適切なサイズでも、取り付け部分の固定が不十分であれば強度が保たれません。専用の金物(垂木留め金具や羽子板ボルトなど)を適切に選定しましょう。
経年劣化も考慮した余裕設計を
特に木材は湿気や経年により徐々に強度が低下するため、初期設計で一定の安全率を見込むことが望まれます。
リフォームの場合は現場状況を優先
既存の建物との取り合いを無視して垂木サイズだけを変えると、施工不良や構造不整合を招く恐れがあります。現場調査と補強設計がカギとなります。
屋根の垂木に関するよくある質問

Q1. 垂木のサイズが小さいと、どんなリスクがありますか?
A. 小さすぎると屋根がたわんだり、雨漏りの原因になったりします。早期の劣化につながる恐れもあります。
Q2. 垂木のサイズを自分で決めても大丈夫?
A. 基本的には設計士や工務店などの専門家と相談してください。構造計算が伴うため、自己判断は危険です。
Q3. 雪が多い地域では垂木サイズは変えるべき?
A. はい、積雪荷重を想定した太めの垂木が必要になります。地域の基準も確認しましょう。
Q4. リフォーム時に垂木のサイズを変えることはできますか?
A. 可能ですが、構造全体との整合性が必要です。現場調査のうえで慎重に検討する必要があります。
Q5. 垂木の間隔(ピッチ)はどのくらいが一般的?
A. 多くは455mmまたは910mmです。狭いほど安定しますが、施工コストが上がる傾向があります。
Q6. 金属製の垂木って使えるの?
A. 使えます。軽量かつ耐久性に優れていますが、住宅の構造や屋根材に適合させる必要があります。
Q7. 垂木の材質は何がいいの?
A. 一般的には杉やヒノキが多く使われますが、強度やコスト、耐久性を考慮して選びましょう。
Q8. DIYで垂木を交換できますか?
A. 危険なのでおすすめできません。屋根の構造に関わる作業は必ず専門業者に依頼してください。
Q9. 垂木のたわみを防ぐ方法は?
A. 適切なサイズ設計とピッチ設定、そして材質選びが基本です。補強材の使用も有効です。
Q10. 見た目では垂木の劣化を判断できますか?
A. 難しい場合もありますが、変色や割れ、たわみが見られる場合は要注意。定期点検が大切です。
9. まとめ|垂木サイズは屋根性能の要
垂木サイズは、屋根の強度や寿命、メンテナンス性に直結する重要な要素です。
住宅の種類や屋根構造、地域特性によって適切なサイズは異なりますが、基本を理解することで、適切な選定ができるようになります。
屋根リフォームや新築設計を検討されている方は、信頼できる業者や建築士と相談のうえ、垂木サイズの最適化を図りましょう。
垂木の知識は、家づくりをより安心・快適にするための第一歩です。
お問い合わせ・無料点検のご予約

- 電話番号:0120-254-425
- メールアドレス:info@maxreform.co.jp
- お問い合わせフォーム:こちらをクリック
- 公式LINE:LINEでお問い合わせ
- 予約カレンダー:こちらをクリック
匿名でのご相談もOKです!皆様のご利用をお待ちしております。
信頼のサービスで、皆様のお住まいをしっかりとサポートいたします✨